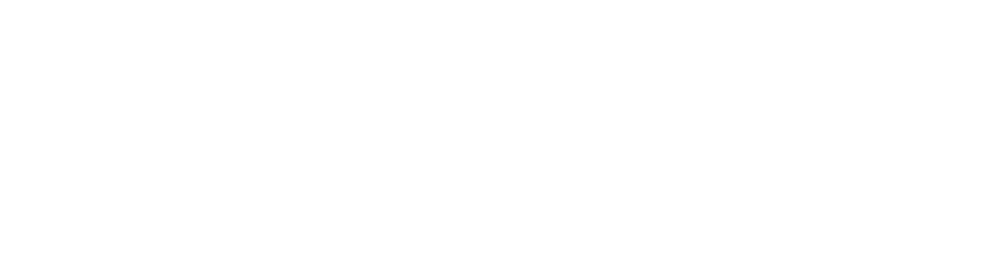渡辺弘・杉原邦生が語る 太田省吾とは、どういう人だったか
2007年に死去した太田省吾。そのひととなりや作品を、周囲はどう感じていたのか。転形劇場時代から太田作品を追いかけ、ジャーナリスト時代には太田にインタビューもしたという、彩の国さいたま芸術劇場 業務執行理事兼事業部長の渡辺弘と、太田の教え子で太田作品の演出助手なども務めた杉原邦生が、“太田省吾とは、どういう人だったか”をそれぞれの視点で語った。2人の対話から見えてくる、“人間・太田省吾”とは?
太田省吾との出会い
お二人は太田さんの作品とご本人、どちらと最初に出会いましたか?
杉原 僕はまずご本人です。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の入学式の後のオリエンテーションで「学科長の太田省吾です」って挨拶があって、「こんなボス猿みたいな人が学科長なのかあ」って(笑)。その数日後に、京都芸術劇場studio21のこけら落としで太田さん演出の『更地(韓国版)』(2001年)を観て、「こんな演劇もあるんだ」と衝撃を受けました。
渡辺 僕は、転形劇場のアトリエで観た『硝子のサーカス』(1976年)が最初ですね。当時友達と劇団をやっていたんですが、彼は品川徹さんが好きで、僕は髭があるせいか瀬川哲也さんに似てると言われて、2人でよく真似をしていたんです。品川さんと瀬川さんはしゃべり方が独特で、モノローグのようだったりと会話にも独自のスタイルがあり、その演技にすごく惹かれました。その後ジャーナリストになって太田さんに会う機会が増え、直接お話するようになったのですが、最初の出会いはそんな感じでしたね。
杉原 そのときのなべ(渡辺)さんの芝居が見てみたいですね!(笑)
渡辺 (笑)。転形劇場の芝居って、後に大杉漣さんが有名になりましたけど、独特なしゃべり方や身体性が特徴で。80年代っていうと、野田秀樹さんや第三舞台などものすごいスピードでしゃべる演劇が多かったから、転形劇場のように超スローな動きで言葉が少ない演劇は非常に独特な存在でした。でも僕は惹かれるものがあって、その後解散するまで、ほぼ観続けていましたね。
太田さんご本人にはどんな印象をお持ちですか?
杉原 僕の在学中、造形大は先生との関係がけっこう密だったので、太田さんや山田せつ子さん、森山直人さんたち教員が僕たちの芝居を観に来てくれて、打ち上げにお呼びしたり、食事に行って感想を聞く、ということがよくありました。太田さんに言われたことで一番に思い出すのは、初めて演出したteuto vol.2『アドア』という作品で、ほかの先生は同級生が書いたテキストのほうを褒めてたんだけど、太田さんだけ「君の演出が良かった」って言ってくれたんです。僕の演出を初めて褒めてくれたアーティストだったので、うれしくてよく覚えています。それと僕に直接言われたわけではないんですけど、太田さんがあるとき、ほかの先生に「杉原は何であんなに演出が上手いんだ? どこで学んでいるんだい?」っておっしゃったそうなんですよ(笑)。言われた先生が「太田さんから学んでいると思います」と言ったら「ああそうか、僕が若いときにはあんな演出はできなかったな」とおっしゃっていたと。それで僕は、どんどん天狗になってしまったわけですが……(笑)。あと、太田さんはお酒が入るとけっこう饒舌で、下世話な話も好きだったし、普通に人間っぽいところがありました。そう思って改めて作品を見ると、作品にもお茶目なところやコミカルなところがあるし、エロスというか人間の色気が描かれているんじゃないかなと思います。
渡辺 確かにちょっとお茶目なところはありましたね(笑)。インタビューでの太田さんは、答えるまでにちょっと間が空くんですよ。決して多くは語らないんですけど、一度考えてからゆっくり話し出す。その間が独特で、僕は劇と人柄が地続きだなって思っていました。またアトリエに芝居を観に行くと、終わった後にそのままよく飲み会が開かれるんですが、太田さんは交友関係が広くて演劇人以外にもいろいろな人がいたので、話題が広がってすごく面白かったです。
宇宙を感じた太田演出版『更地』
転形劇場は1988年に解散。その後、太田さんは藤沢市湘南台市民センターの芸術監督に就任します。そんな太田さんの動きを渡辺さんは当時、どんなふうに感じましたか?
渡辺 まず劇団が解散したのはショックでした。でも自分も劇団をやっていたから、やっぱりそういう時期が来るだろうな、意外と早かったなと思いましたね。その経緯について、当時は太田さんに詳しく聞くことがなかったんですけど、太田さんが劇場の芸術監督になられたのにはびっくりしました。蜷川幸雄さんがアングラから商業演劇に行ったように、人はどこかでグッと歩く道を変えることがありますが、太田さんも地道な劇団活動から能楽堂での『小町風伝』、“沈黙劇『水の駅』”で地位を確立して、世界に飛び出したり、アトリエを作ったり、さらに劇場をやるのかと。あの太田さんがどういう劇場運営をするんだろうと興味を持って見ていましたね。
その湘南台市民センターで、『更地』も上演されました。
渡辺 僕も観に行きました。湘南台市民センターはプラネタリウムみたいに天井が高くて、不思議な空間なんですが、そこへ老夫婦の岸田今日子さんと瀬川さんが現れて会話を繰り広げるんです。今日子さんは自由な演技だし、瀬川さんは頑なに太田スタイルを貫いているし、不思議な夫婦だったなあ(笑)。劇中、白い布がパーっと舞台にかけられて、新たな更地が生まれるんだけど、空間の印象も相まって最後は宇宙という感じがしました。でも杉原版では、若い2人が演じるんだよね?
杉原 はい。僕が2012年に『更地』を初めて演出した時は東日本大震災の翌年ということもあって、世の中にまだ震災の残り香があり、社会がこのあとどこへ向かっていったらいいかを考えざるを得なかった時期でした。という状況と、「いつか太田さんの作品を上演したい、やるなら『更地』が良い」と考えていたので、太田さんが阪神淡路大震災の翌年に『更地』を上演して観客の心を打ったという話を思い出し、『更地』を上演するなら今かもしれないと思ったんです。ただ、太田さん演出の『更地』では、過去を思い出したり、過去を掘り起こす印象が強かったんですけど、僕らはこれから先のことを考えないといけないと思っていたので、演出で何とか印象を変えられないかなと考えて、そこから若い俳優でやる、というアイデアが浮かびました。その目線で考えると、新婚の夫婦が何もない更地にやってきて未来を想像するようにも、あるいはすでに命を奪われたある夫婦がかつて家のあった場所にやってきて、自分たちのあるはずだった未来を演じているようにも見えるんじゃないか、そうなれば、観客も夫婦と一緒に先のことを考えられるのではないかと思って。また、戯曲だけ読むと夫婦観やジェンダー観はちょっと昭和の匂いがするんですけど、それを若い俳優がライトに演じることで昭和らしさがファンタジーになるというか(笑)、あまり引っ掛かりがなくなると感じたので、再演でも若い俳優でやることにしました。
渡辺 なるほど、確かにそのほうがいいかもしれないね。若い俳優が素のままで演じたほうが、作品の幅を広げられるかもしれない。
杉原 ええ。夫婦に限らず、2人が親子や姉弟に見えるかもしれないし、男とか女といったことを超えて、宇宙の中の地球に立つ人間2人が、未来を再構築していこうとする話にも見えたらいいなと思っています。
渡辺 でも俳優にとっては試練だろうね。太田さんの作品は言葉が少ないから、演技者として内面をどう埋めていくかが問われるし、とても大変だと思う。
人間の存在をしっかり描くこと
初演時も今回も、杉原さんは「太田さんの芯をブラさずに自分なりの演出を」と意気込みを語っていらっしゃいました。杉原さんが思う、“太田さんの芯”とはどんなところですか?
杉原 僕は太田さんから、人間の存在を舞台上でしっかり描くということと、社会に対して作品をどういう態度で発表するかを常に自問自答し、自己批評し続けるということを学んだと思っています。逆にそこさえブレていなければ究極、ゆっくり歩かなくても『水の駅』になるだろうし、巨大な白布を使わなくても『更地』になるんじゃないかなって。なので、ちゃんとテキストに向き合ったうえで、人間の存在を舞台上でしっかりと描きたいと思います。
また渡辺さん、杉原さんお二人から“宇宙”というキーワードが出ました。太田さんの作品のどのようなところに“宇宙”を感じるのでしょうか?
杉原 大学の授業の最初のほうで、「Power of Ten」という映像を見ました(1968年にチャールズ・イームズと妻のレイによって制作された教育映画)。アメリカの公園でピクニックシートに寝転んでいる男女がいるんですけど、そこから10の倍数でどんどん引いていくと、大陸が見え、地球が見え、銀河系が見えてくる。その後、今度は寄っていくと、最後は人間の皮膚の中まで入り込んで、今度はそこがまた宇宙のように見えてくるんですね。その映像について太田さんが何て言っていたか、正確には覚えてないんですけど、ただ「演劇はこういうことが大事だ」というようなことを言っていたんじゃないかと思います。以来、演劇を作るうえで“宇宙の中に地球があって、国があって、土地があって、そこに僕らがいる”という前提を考えるようになったし、太田さんの作品を観るときも「太田さんは今、どういう宇宙の中でこの作品を作ってるんだろう?」という視点で観るようになりました。なので、「太田さんは宇宙だ!」という先入観が僕の中にあるのかもしれませんが(笑)、ただ実際、『更地』の言葉や空間には、宇宙を感じる要素がちりばめられていると感じます。
渡辺 太田さんは引き揚げてこられた方で、『水の駅』にしろ、『風の駅』『地の駅』にしろ、ずーっと遠くから人類がやってくるという風景が描かれています。ご自身が体験した風景が、そういった部分に無意識に立ち現れるのかもしれませんね。『更地』に関しては、舞台が円状だったということもあるんですけど、老夫婦と観客が一体になって、バブルの中にいる感じがしてきたんですよ。それが宇宙っぽいなと。また太田さんは時間を歪ませる作り手で、僕らが生きている時間をスローにして感覚を変えてみせたり、“どこか”へ連れていってくれたりもする。そういったところからも宇宙を感じるのかもしれません。
太田さんからの教え──舞台の高さは虚構度の高さ
太田作品は上演される空間も非常に大事だということですね。
杉原 僕、太田さんから空間の重要さも学んだと思っています。「演劇は空間がなければ俳優も言葉も成立しない。まずは空間」と。だから、僕も上演する場所がどういう場所かということをまず考えます。また太田さんは「舞台の高さは虚構度の高さだ」とも言っていて、「客席と舞台が同じ地平だったら観客も同じ気持ちで舞台を観るけど、舞台面が高くなればなるほど遠いもの、虚構度の高いものとして舞台を観る。だからまずは自分が観せたいものを、どの高さで観せるか考えろ」と。今もその点は毎回意識して、どういう場所でどういう舞台の高さで上演するか、考えています。『更地』に関しては、3つの劇場をツアーしますが、どの劇場もダイナミックな空間なので、その場所に対して“更地”というエリアをどう設定するかを考えていきました。太田さんは真っ黒な空間に白い幕をかけて“まっさらな更地”を表現したけど、僕はそれだと空間が狭まる気がしたので、まずは白でエリアを区切り、そこに黒い布をかけて空間を広げる演出にしました。別にあえて太田さんと違うことをやりたかったわけではなく、僕が考えたらたまたま太田さんの演出と白黒反転になったのですが、それを軸に全体を考えていきました。
杉原さんが太田さんから教わったことは、本当にたくさんありそうですね。
杉原 そうですね、思い出せないくらい。太田さんから教わったことは、本当にたくさんあります。
愛情深い先生で、誠実な作り手
改めて、演出家の先輩であり先生としての太田さん、アーティストとしての太田さんは、お二人にとってどんな存在ですか?
杉原 先生としてはすごく厳しかったです。作品に対する作り手の甘えを絶対に見逃さなかったし、だからすごく鍛えられたと思います。その一方で太田さんはとても愛情深い方でした。太田さんは2007年7月にお亡くなりになり、僕はその年の3月に大学院の修士課程を修了したんですが、当時は闘病中で入院なさっていたのに、学位授与式に駆けつけてくださいました。で、大学院生だけ修了証書を手渡ししてくれて。
渡辺 太田さんは演劇界の中では独特な方だと思います。活動初期に沖縄の返還問題について三部作を書いていたり、割と早い時期にポーランドで公演したりと、アングラ全盛期のあの頃、鈴木忠志さん、唐十郎さん、別役実さん、蜷川幸雄さんたちが華々しく活躍する中で、自分はどうやっていくべきか、誠実に時代と演劇に向かい合いながら考えていたと思うんです。いわゆるスターではなかったかもしれないけど、その誠実さは尊敬しますし、結果的に独自の地位を築かれたのではないでしょうか。
杉原 そんな太田さんの作品を、僕ら世代の演出家が上演することについて、渡辺さんはどう思われますか?
渡辺 さいたまゴールド・シアターの『水の駅』は、あなたが2019年に上演した『水の駅』を観なければ思いつかなかったと思います(笑)。
杉原 あははは! 終演後すぐ、「邦生くん、これゴールドでやったら面白いんじゃない?」って声をかけてくださいましたよね。
渡辺 あのときはすごい時間でしたよ! 上演を観ながら頭の中でワーッと太田さんのことが思い出されて、『小町風伝』は老婆の幻想、『更地』も老夫婦と、太田さんの作品には高齢者が出てくるなぁと気づいたんです。そうやって考えると、太田作品には長い人生を背負って生きてきた人たちの存在感が描かれていて、現代能のようにも感じられるなって。そういう点で、太田さんの芝居はこれからもっとやられても良いのではないかと思いますが、太田さんの作品に向き合うのは俳優にとっても演出家にとっても大変な作業だと思います。外側だけ華やかにやればいいということでは一切なく、自分の内に、自分と社会との関係や記憶など、すべてを内在させないといけないので。その作業ができる演出家もそう多くはいないと思う。杉原さんはこれからずっと、太田作品を伝えていく役目を背負っていかないといけないのではないかな。
杉原 そうしたいですね。
渡辺 かつ、太田さんが何をしたかったということも考え続けないといけないですよね。それには能などいろいろなことも結びつけながら考えていく必要があるだろうなと思います。
使命感を持って挑む、さいたまゴールド・シアター最終公演『水の駅』
さいたまゴールド・シアターの最終公演『水の駅』については、今どんな演出プランを持っていらっしゃいますか? 2019年の『水の駅』のようには……。
杉原 いかないですよね(笑)。あの時は傾斜舞台もあり、身体表現の比重がかなり大きかったので。でも渡辺さんから「ゴールド・シアターで『水の駅』を」とアイデアをいただいて、直感で面白そうだと思いました。また僕が大きな影響を受けた蜷川さんのレガシーであるゴールド・シアターと、恩師の太田さんが遺した作品をつなげる、こんな大役を担わせていただけるなんて本当にありがたいし、実際僕ぐらいしかやれる人はいないんじゃないかなって思うので(笑)、今回はある種の使命感を感じています。なので2019年に上演した『水の駅』のことはいったん忘れて、彩の国さいたま芸術劇場 大ホールという空間をダイナミックに使いつつ、彼らの餞として意義のあるものにしたいなと。大きな空間でやることで、太田作品にある宇宙の中の人間みたいなスケール感をこれまで以上に表現できるとも思います。また今は言葉がすごく力を持っているので、あえて言葉を排した表現で、僕らが社会に何が提示できるかをきちんと考えたいですし、その点で演劇的にも社会的にも意味がある公演にしたいと思っています。
渡辺 蜷川さんと太田さんって当時は距離があったと思いますが、今回はゴールド・シアターが結びつけてくれました。杉原さんには、蜷川さんと太田さんから受け取ったものをゴールド・シアターに注ぎ込んで、新たな“宇宙”を作ってほしいですね。実際、ゴールド・シアターに向き合うと、岩松(了)さんにしろ岩井(秀人)くんにしろ、彼らが体験してきた時間、原爆の話や戦争の話に触れざるを得なくなる。ゴールド・シアターの存在って、そういう意味でも面白いんです。杉原さんにとっても、これはすごく大事な仕事になると思いますよ。
杉原 そうですね。責任重大ですが本当に楽しみです!
取材・文:凛
- 本対談は2021年10-11月に上演のKUNIO10『更地』公演会場で配布した無料パンフレットに掲載したもののロングバージョンです。対談は2021年9月25日に行いました。
渡辺弘
埼玉県芸術文化振興財団業務執行理事兼事業部長。1953年栃木県生まれ。演劇ジャーナリストとして活動後、銀座セゾン劇場の開設準備などに携わる。東急文化村シアターコクーンの運営・演劇制作やまつもと市民芸術館の開設準備・企画運営を経て、2006年から現財団に携わる。
さいたまゴールド・シアター最終公演『水の駅』
作:太田省吾
構成・演出・美術:杉原邦生
出演:さいたまゴールド・シアター / 井上向日葵 / 小田豊
2021年12月19日(日)〜26日(日) *21日は休演
会場:彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
https://kunio.me/stage/sgt/